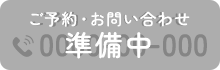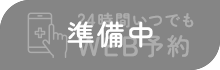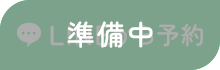- 便意があるのに出ない・出口で詰まってなかなか出ないという方へ
- 便意があるのに出ない・出口で詰まる原因は?
- 便秘が続くと…
- 便意があるのに出ない・出口で詰まる場合に考えられる病気
- 便意があるのに出ない・出口で詰まるときの対処法
- 便意があるのに出ない・出口で詰まる場合の検査
- 便意があるのに出ない・出口で詰まるときの治し方
便意があるのに出ない・出口で詰まってなかなか出ないという方へ
 便秘とは、単に排便回数が週3回未満に減ることだけを指すのではありません。
便秘とは、単に排便回数が週3回未満に減ることだけを指すのではありません。
たとえ毎日排便があっても、残便感や排便困難、硬い便といった症状があれば、それは便秘と言えます。快適な排便ができない状態はすべて便秘と捉え、当院では治療の対象としています。便秘は特に女性の患者様に多く、加齢に伴いその悩みは深刻化する傾向があります。男性の患者様も70歳を過ぎると便秘の頻度が増加します。
便秘の原因や状態は患者様によって様々です。当院では消化器内科専門医が、適切な検査で原因を究明し、患者様のライフスタイルや状態に合わせた治療計画をご提案します。作用の異なる多様な新薬も登場しており、市販薬で改善しなかった患者様にも効果が期待できます。漢方薬の併用や、再発防止のための丁寧な生活習慣指導も行っております。
便秘の背景には、何らかの疾患が隠れている可能性もございます。また、便秘自体が他の病気の発症リスクを高めることもありますので、お悩みの方はどうぞお気軽に当院へご相談ください。
便意があるのに出ない・出口で詰まる原因は?
患者様が便意を催しているにも関わらず、なぜ排便が困難になるのでしょうか。
その状態を引き起こす主な原因として、以下のものが考えられます。
生活習慣の乱れ
患者様の生活リズムの乱れ、特に睡眠不足は自律神経の均衡を損ないます。
自律神経は、消化や代謝、呼吸、循環といった機能を調整しているため、その乱れは排便リズムの不調に直接繋がることがあります。
偏った食事
腸内には、善玉菌や悪玉菌をはじめとする多種多様な細菌が、約40兆個も存在しています。これらの菌が適切なバランスを保つことが、患者様の心身の健康には不可欠です。
しかし、不規則な生活習慣や偏った食事は悪玉菌の増殖を促し、腸内環境の乱れを招きます。
こうした腸内環境の悪化が、患者様が便意を感じても排便できないという状況を招くことがあるのです。
崩れた腸内環境
患者様の腸内には、およそ40兆個、数百種類もの腸内細菌が生息しています。心身の健康を維持するため、悪玉菌やその他の菌、善玉菌といった腸内細菌が適切な均衡を保つことは不可欠です。しかし、不規則な生活や偏った食事は悪玉菌の増殖を招き、腸内環境を乱します。
このバランスの崩壊が、便意はあっても排便できないという状態を引き起こす一因となります。
精神的なストレス
自律神経のバランスは、腸の機能に直接影響を及ぼします。
患者様が精神的なストレスにさらされると、自律神経を構成する交感神経が活発化します。
交感神経には腸の蠕動運動を抑える働きがあるため、継続的なストレス環境は、患者様の慢性的な便通の悩みに繋がるのです。
便秘が続くと…
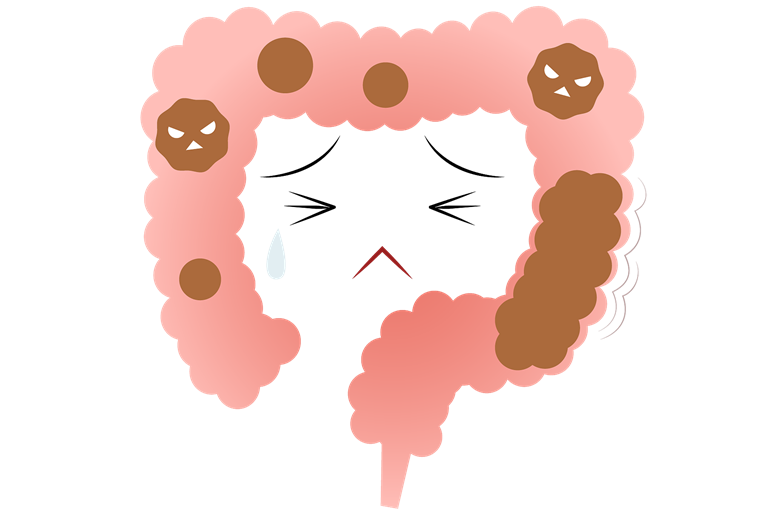 腸内に長時間便がとどまることで、水分が過剰に吸収されて便がさらに硬くなり、排便がますます困難になります。また、便が出口付近で詰まる状態が慢性化すると、肛門や直腸の感覚が鈍くなり、「出したいのに出せない」という悪循環に陥ることもあります。
腸内に長時間便がとどまることで、水分が過剰に吸収されて便がさらに硬くなり、排便がますます困難になります。また、便が出口付近で詰まる状態が慢性化すると、肛門や直腸の感覚が鈍くなり、「出したいのに出せない」という悪循環に陥ることもあります。
さらに、腸内環境の悪化により、肌荒れや口臭、免疫力の低下など全身への影響も無視できません。重症化すると「直腸瘤」や「便塞栓(べんそくせん)」といった病的な状態につながる場合もあります。
便意があるのに出ない・出口で詰まる場合に考えられる病気
便秘は、様々な疾患が原因となっていることがあります。
消化器系疾患をはじめ、主に以下のものが考えられます。
過敏性腸症候群
不安定型(便秘と下痢の繰り返し)や慢性下痢型、粘液分泌型など、いくつかのタイプがあります。腹部膨満感や腹痛を伴う便通異常が主な症状として現れます。
ストレスによる自律神経の乱れや、腸の過剰な運動が原因とされています。
炎症性腸疾患
(潰瘍性大腸炎・クローン病)
潰瘍性大腸炎とは、大腸の粘膜にびらんや潰瘍が生じる、原因不明の炎症性腸疾患です。寛解期と活動期を繰り返し、患者様には下痢や血便、粘血便などの症状が現れます。
クローン病も、炎症性腸疾患の一種です。患者様には発熱や腹痛、血便、下痢、体重減少などの症状が見られます。腸管の炎症や狭窄が、腸閉塞や便秘を引き起こすこともあります。
痔
切れ痔(裂肛)とは、勢いのある下痢や硬い便が原因で、肛門の皮膚が切れてしまう状態です。
患者様には、痛みや出血、便秘、便が細くなるといった症状が現れます。慢性化した患者様の場合、傷の治癒過程で肛門が狭くなる肛門狭窄をきたすことがあります。
重症化すると便が鉛筆のように細くなりますが、一度や二度の発症では稀です。肛門狭窄が進行した患者様には、当院での手術が必要となる場合もございます
便意があるのに出ない・出口で詰まるときの対処法
便意はあるものの排便が困難な患者様へ、日常生活で試せる改善策や対処法をご説明します。
この症状でお悩みの場合は、実践可能なものから取り入れていただくことを当院は推奨しています。
食生活の改善
 食生活に乱れがある患者様は、まずその改善から始めることが重要です。お通じの悩みを解消するには、栄養バランスの良い食事とともに、2種類の食物繊維を摂ることが不可欠です。
食生活に乱れがある患者様は、まずその改善から始めることが重要です。お通じの悩みを解消するには、栄養バランスの良い食事とともに、2種類の食物繊維を摂ることが不可欠です。
水溶性食物繊維は、腸内の善玉菌を増やして便を柔らかくし、不溶性食物繊維は便のかさを増す働きをします。また、食物繊維には過剰な糖や脂質を排出する作用もあるため、便秘の解消には欠かせない栄養素です。
きのこ類や根菜、キャベツ、果物などに豊富に含まれているため、日々の食事で意識的に摂取することを当院は推奨しています。
腸内環境を整える
 腸内環境を整えるには、善玉菌を増やし、悪玉菌の活動を抑制することが不可欠です。そのために、当院では患者様に二つのアプローチを推奨しています。
腸内環境を整えるには、善玉菌を増やし、悪玉菌の活動を抑制することが不可欠です。そのために、当院では患者様に二つのアプローチを推奨しています。
一つ目は、生きた善玉菌である「プロバイオティクス」の摂取です。納豆やヨーグルト、乳酸菌飲料などに含まれる乳酸菌やビフィズス菌がこれにあたります。ただし、これらの菌は腸内に定着しないため、毎日継続して摂取することが肝心です。
二つ目は、既存の善玉菌を育てる「プレバイオティクス」を食事に取り入れる方法です。オリゴ糖や食物繊維がこれに該当し、ごぼうや玉ねぎ、バナナ、大豆といった食品から摂取できます。ただし、オリゴT糖は一度に多量摂取すると、お腹が張るなどの不調をきたすことがあります。患者様には、1日2〜10gを目安に少量から始め、体に慣らしていくことをお勧めします。
腸内環境はすぐには改善しないため、焦らず食事改善に取り組むことが重要です。
こまめな水分摂取

水分補給というと飲料を思い浮かべるかもしれませんが、食事からも摂取が可能です。
例えば、キャベツやきゅうり、にんじんなどは水分を豊富に含んでいます。これらの食材は、便を柔らかくする作用が期待できる水溶性食物繊維も多いため、患者様が日々の食事で意識的に摂取することをお勧めしています。
もちろん、食材からだけでなく、飲料からの水分補給も重要です。患者様に必要な水分量は、体重や性別、運動量によって異なりますが、体重60kgの成人男性の場合、飲み水から1日1.2L程度が必要とされています。
水分補給の際は、利尿作用のあるコーヒーやアルコールは避け、白湯や水を飲むよう心がけましょう。
便意があるのに出ない・出口で詰まる場合の検査
 長引く便秘は、大腸がんなどの疾患が原因の場合もあるため、大腸カメラ検査で原因を特定することが重要です。
長引く便秘は、大腸がんなどの疾患が原因の場合もあるため、大腸カメラ検査で原因を特定することが重要です。
当院では、専門医が鎮静剤を使用し、患者様がリラックスした状態で受けられる質の高い検査をご提供しています。また、必要に応じて超音波(エコー)検査や血液検査も行い、正確な診断から適切な治療へと繋げます。
一方、特定の疾患が関与しない便秘は、市販薬の常用やストレス、便意の我慢、運動不足、食事など、多くの要因が複雑に絡み合っています。そのような場合でも、当院は便秘のタイプを正確に見極め、患者様のライフスタイルに配慮した治療を行います。
便意があるのに出ない・出口で詰まるときの治し方
便秘の原因疾患が判明した場合、当院はその治療を優先します。
原因が特定できない患者様にも、生活習慣の見直しと薬物療法で症状の改善を図ります。
生活習慣の改善
生活習慣の改善は、便秘の解消と再発防止に役立ちます。
食物繊維や水分を十分に摂り、規則正しい生活を送るよう、当院は患者様にお伝えしています。
また、決まった時間にトイレへ行く習慣や、便意を我慢しない排便習慣の確立も重要です。
薬物療法
便秘治療には主に下剤を用いますが、漢方薬や便の水分を調整する薬など、選択肢は多様です。
当院では患者様の便秘のタイプや症状、生活習慣を考慮して処方します。再発を防ぐには、下剤のみに頼らず、生活習慣の改善を併行することが重要です。