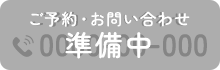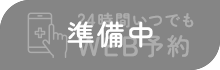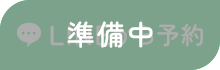- 下痢・便秘・腹痛が続く「過敏性腸症候群(IBS)」
- 過敏性腸症候群のタイプと症状
- 過敏性腸症候群の最大の原因はストレス?
- 過敏性腸症候群の検査・診断
- 当院の過敏性腸症候群治療について
- 薬だけに頼らない!過敏性腸症候群の食事・生活
- ストレスからくる腹痛・下痢は何科を受診すべき?
- よくある質問
下痢・便秘・腹痛が続く「過敏性腸症候群(IBS)」
 過敏性腸症候群(IBS:Irritable Bowel Syndrome)とは、検査では異常が見つからないのに、下痢や便秘、腹痛といった腸の不調が慢性的に続く病気です。日本人の約10~15%がIBSと言われており、決して珍しい病気ではありません。男女比は1:2と女性に多く、20-30代の若年成人で頻度が高いです。
過敏性腸症候群(IBS:Irritable Bowel Syndrome)とは、検査では異常が見つからないのに、下痢や便秘、腹痛といった腸の不調が慢性的に続く病気です。日本人の約10~15%がIBSと言われており、決して珍しい病気ではありません。男女比は1:2と女性に多く、20-30代の若年成人で頻度が高いです。
血便や発熱、体重減少などは生じません。また、機能性ディスペプシアやうつ病、不安障害などを併存することも多いです。
腸の動きが過敏になったり、腸内環境が乱れたりすることで症状が現れると考えられています。特にストレスや生活習慣の乱れが症状の悪化と関係しているケースが多く見られます。
IBSは命に関わる病気ではありませんが、仕事や外出が不安になったり、人間関係に影響が出たりと、生活の質(QOL)が大きく下がってしまう方も少なくありません。
しかし、適切な治療と生活改善で症状はコントロールできる病気です。
過敏性腸症候群のタイプと症状
過敏性腸症候群(IBS)は、人によって現れる症状が異なり、主に4つのタイプに分けられます。それぞれの特徴を知ることが、適切な治療につながります。
下痢型IBS
下痢型IBSは、突然の腹痛や下痢を繰り返すタイプです。特に通勤途中や外出先で急にトイレに行きたくなることが多く、「トイレに行けない場所に行くのが怖い」と感じる方もいます。
緊張した時やストレスがかかった時に症状が悪化しやすいのが特徴です。
便秘型IBS
便秘型IBSは、慢性的な便秘が続くタイプです。排便してもすっきりしない、お腹の張りや違和感を感じることが多く、「便は出るけど硬く少量」といった症状もよくみられます。
腸の動きが鈍くなっていることが原因と考えられています。
交代型IBS
交代型IBSは、下痢と便秘を繰り返すタイプです。調子が良いと思っていても急に下痢になったり、逆に便秘が続いたりと症状の変動が大きく、自分でもコントロールが難しいと感じる方が多いです。
体調やストレス、食事の影響を受けやすいことが特徴です。
ガス型IBS(ガス漏れ型)
ガス型IBSは、おならが頻繁に出る、ガスが溜まってお腹が張るタイプです。周囲に気づかれることを過剰に心配してしまい、人前に出ることや会話することが怖くなるケースもあります。
腸内環境の乱れや腸の動きの異常が関係していると考えられています。
過敏性腸症候群の最大の原因はストレス?
過敏性腸症候群(IBS)の原因は、明確に1つに特定できるものではありません。現在、以下のような要因が関係していると考えられています。
ストレスや緊張
IBSの大きな特徴は、ストレスや緊張で症状が悪化しやすいことです。
職場や学校、人間関係のストレスが腸の働きに影響し、便通異常や腹痛を引き起こします。実際に「外出前になるとお腹が痛くなる」「仕事が忙しいと下痢になる」という方は少なくありません。
自律神経の乱れ
腸は自律神経の影響を強く受ける臓器です。ストレスや不規則な生活などで自律神経のバランスが乱れると、腸の動き(蠕動運動)が過敏になったり、逆に鈍くなったりしてしまいます。
これが便秘や下痢につながると考えられています。
腸と脳のつながり(腸脳相関)
腸と脳は互いに密接に影響し合っています。これを腸脳相関(ちょうのうそうかん)と呼びます。精神的ストレスが腸の状態に影響し、腸の不調がさらに気分の不安定さを招くという悪循環に陥ることもあります。
腸内環境の乱れ
腸内の善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れることで、ガスが発生しやすくなったり、腸の動きが乱れることがあります。腸内細菌のバランスは、食生活やストレスの影響を受けやすいとされています。
食生活の乱れ
不規則な食事や、脂っこいもの・刺激物・アルコールなどを摂りすぎると、腸に負担がかかり、IBSの症状が悪化しやすくなります。
過敏性腸症候群の検査・診断
 過敏性腸症候群(IBS)は、「検査で異常が見つからないのに、腸の症状が続く病気」です。そのため、診断ではまず他の重大な病気が隠れていないかをしっかり調べることが重要です。
過敏性腸症候群(IBS)は、「検査で異常が見つからないのに、腸の症状が続く病気」です。そのため、診断ではまず他の重大な病気が隠れていないかをしっかり調べることが重要です。
まず、当院では大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)を行い、大腸がんや炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)などの病気を除外します。また、必要に応じて血液検査や便検査、腹部エコー検査なども行います。
これらの検査で異常が見つからず、慢性的に下痢や便秘、腹痛といった症状が続いている場合に、「過敏性腸症候群(IBS)」と診断します。
当院の過敏性腸症候群治療について
当院では、過敏性腸症候群(IBS)の治療を「薬だけに頼らない」「患者様一人ひとりに合わせた治療」を大切にしています。IBSは生活やストレスの影響も大きいため、単に薬を処方するだけでなく、症状やライフスタイルに合わせたオーダーメイドの治療をご提案しています。
薬物療法
 IBSは症状タイプ(下痢型・便秘型・交代型・ガス型)に合わせて薬を選びます。
IBSは症状タイプ(下痢型・便秘型・交代型・ガス型)に合わせて薬を選びます。
- 整腸剤:腸内環境を整え、ガス型や腹部膨満感に効果的です。
- 便通調整薬:下痢型にはロペミン、便秘型にはリンゼスなどを使用。
- 漢方薬:体質や症状に合わせ、桂枝加芍薬湯や大建中湯などの漢方薬も併用します。
- 抗不安薬・抗うつ薬:ストレスや緊張で症状が悪化する場合、腸と脳のバランスを整える目的で少量使用することもあります。
食事・生活習慣の見直し
食事内容や食べ方、生活リズムを見直すことで症状が改善するケースも多いため、食事指導や生活改善のアドバイスも行っています。特に、脂質・カフェイン・アルコールなど腸への刺激となるものは控えるよう指導します。
ストレスケアも重視
IBSはストレスとの関係が深いため、必要に応じてストレスマネジメントのアドバイスも行っています。「お腹の悩みがストレス」になっている方にも、心理面へのサポートを意識しています。
薬だけに頼らない!過敏性腸症候群の食事・生活
 過敏性腸症候群(IBS)は薬だけで治す病気ではありません。腸に負担をかけない食事や生活習慣の見直しが、症状を和らげる重要なポイントです。当院では治療と併せて、以下のような生活改善アドバイスを行っています。
過敏性腸症候群(IBS)は薬だけで治す病気ではありません。腸に負担をかけない食事や生活習慣の見直しが、症状を和らげる重要なポイントです。当院では治療と併せて、以下のような生活改善アドバイスを行っています。
朝食は抜かずに規則正しい食事を
腸の働きを整えるために、朝食を抜かないことが基本です。毎日決まった時間に食事をすることで腸のリズムも安定します。
腸内環境を整える食事
ヨーグルトや納豆などの発酵食品、水溶性食物繊維を含む食材は、腸内環境を整える助けになります。
ただし、食物繊維は摂りすぎるとガスや腹痛の原因になるため、自分の体調に合わせて少量から取り入れることが大切です。
刺激物・脂っこいものは控えめに
脂っこい料理やカフェイン、アルコールは腸を刺激し、下痢や腹痛を悪化させることがあります。
調子が悪いときは、刺激物は控えめにするのがポイントです。完全に禁止する必要はなく、体調に合わせて調整しましょう。
ストレスケアと適度な運動
IBSはストレスによる悪化が多い病気です。
ウォーキングなどの軽い運動や趣味の時間を意識的に作り、リラックスすることも重要です。
FODMAP食事療法
症状が強い方には、「FODMAP(フォドマップ)食事療法」という食事法が有効なこともあります。これは腸で発酵しやすい糖質を制限する食事法です。医師と相談しながら無理のない範囲で取り入れることをおすすめします。
低FODMAP食品と高FODMAP食品の例
| 食べてもよい(低FODMAP) | 控えたい(高FODMAP) |
|---|---|
| 白米・うどん・そば きゅうり・なす・にんじん バナナ(熟していないもの)・みかん チーズ(ハードタイプ) 鶏肉・魚・卵 砂糖(少量) |
小麦パン・ラーメン 玉ねぎ・にんにく・キャベツ りんご・洋ナシ・すいか 牛乳・ヨーグルト はちみつ・キシリトール入り製品 |
低FODMAP食品の取り入れ方
FODMAP食事療法は、症状が強いときの一時的な対処法として取り入れることが多いです。
完全に制限するのではなく、食事内容を見直しつつ、自分に合わない食品を見つけて控えることが大切です。
- 2〜6週間程度、低FODMAP食品を中心に食事を調整
- 症状が改善すれば、徐々に高FODMAP食品を試し、自分に合う範囲を探していきます
- 長期間の厳しい制限は腸内環境の悪化につながるため注意
ストレスからくる腹痛・下痢は何科を受診すべき?
仕事や学校、日常生活のストレスがきっかけで、腹痛や下痢を繰り返している方は多くいらっしゃいます。
「ストレスが原因だから仕方ない」と我慢している方も多いですが、実際には腸が過敏になっている「過敏性腸症候群(IBS)」の可能性があります。
このような症状が続いている場合は、消化器内科の受診がおすすめです。
消化器内科では、大腸カメラ検査などで大腸がんや潰瘍性大腸炎などの病気がないことを確認しつつ、IBSと診断した場合は腸の動きを整える薬や整腸剤、漢方薬などで治療を行います。
ストレスがあっても、「腸の病気」としてきちんと治療することで症状をコントロールできる病気です。
「自分はただのストレスだから…」と我慢せず、ぜひ当院の消化器内科へお気軽にご相談ください。
よくある質問
過敏性腸症候群に効く市販薬はありますか?
下痢止めや整腸剤など市販薬で一時的に症状を抑えることは可能ですが、根本的な治療には専門医の受診がおすすめです。
ビオフェルミンは過敏性腸症候群に効果がありますか?
ビオフェルミンなどの整腸剤は腸内環境を整えるサポートになります。ただしIBSの症状が強い場合は、医師の指導のもと治療することが大切です。
IBSの薬は一生飲み続ける必要がありますか?
症状が安定している間は薬を中止できる方も多くいます。症状に応じて薬の調整を行いますので、医師と相談しながら進めましょう。
IBSは難病指定されていますか?
いいえ。IBSは命に関わる病気ではないため、国の難病指定には含まれていません。ただし、日常生活に支障が出ることもある病気です。
IBSでおならが増えることはありますか?
はい。特にガス型IBSではおならが増えたり、ガスが溜まってお腹が張る症状がよく見られます。
IBSのおならは臭いが強いのでしょうか?
腸内環境の乱れがある場合はガスの臭いが強くなることもあります。整腸剤や食事改善が効果的なことがあります。
IBSと診断されたら必ず薬を飲む必要がありますか?
症状が軽い場合は薬を使わず生活改善中心で治療することも可能です。症状に合わせて治療方針を決めます。
IBSにストレスはどのくらい関係していますか?
ストレスはIBSの最大の悪化要因といえます。ストレスの強い環境下では症状が出やすくなる方が多いです。
市販の漢方薬はIBSに効きますか?
市販の漢方薬で症状が改善することもありますが、体質に合わない薬を飲むと悪化する場合もあるため、医師の診察を受けることをおすすめします。
ビオフェルミンはいつまで飲めば良いですか?
整腸剤は比較的安全な薬ですが、効果を実感できない場合は続ける必要はありません。効果の程度を見ながら調整しましょう。
IBSは精神科に行くべき病気ですか?
IBSは腸の病気(消化器内科の病気)です。ストレスは影響しますが、精神科を受診する必要はありません。
IBSのおならの音が気になって外出できません。治療できますか?
ガス型IBSは薬や食事指導で改善できる場合が多いため、消化器内科で治療することをおすすめします。
IBSは夜間に症状が出ますか?
IBSの症状は昼間や起床後に出ることが多いですが、人によっては夜間に腹痛やガスが気になることもあります。
IBSの薬は眠くなる副作用がありますか?
腸の動きを整える薬では眠気は少ないですが、抗不安薬などを併用する場合は眠気が出ることがあります。医師と相談しながら使用します。
ストレスがなくなればIBSは自然に治りますか?
ストレスは重要な要因ですが、それだけが原因ではありません。ストレス対策だけで自然治癒することは少なく、薬や生活改善も併用することが大切です。