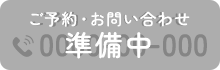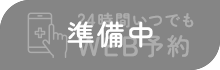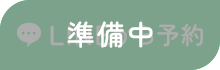当院の内科の特徴
総合内科専門医が内科全般を幅広く対応
 当院では、日本内科学会が認定する総合内科専門医の院長が、患者様の診療を担当いたします。
当院では、日本内科学会が認定する総合内科専門医の院長が、患者様の診療を担当いたします。
脂質異常症や糖尿病、高血圧をはじめとする生活習慣病など、内科全般にわたり治療を行います。
丁寧な問診と診察を基本に、各種検査を用いて的確な診断を導き出します。
また、運動や食事を中心とした生活習慣の改善を重視し、お薬は必要最小限に留めながら症状の改善を目指します。
総合内科専門医とは?
総合内科専門医とは、幅広い内科全般の知識を有しており、患者様の全身を総合的に診て、的確な診断を下す専門医です。どの診療科にかかればよいか分からないような症状も総合的に診療します。
これは、従来の一般内科の役割を、さらに専門的に発展させた存在とも言えます。
例えば「腹痛」という症状に対し、消化器の専門家は消化器疾患をまず考えますが、総合内科専門医は免疫やホルモンの問題など、より広い可能性を視野に入れて診療を進めます。
このように、特定の臓器に限定されず、患者様を全人的に診察できることが総合内科専門医の大きな強みです。
こんな症状は内科までお越しください
下記のような症状や、普段と体調が違うと感じる患者様は、お早めにご相談ください。
早期の発見と治療が、早い回復に繋がります。

- 倦怠感、頭痛
- 発熱、微熱
- 喉の痛み
- 鼻づまり、鼻水
- 食欲不振、吐き気
- 腹部膨満感
- 下痢、便秘
内科で診療する疾患
急性疾患
- 上気道感染症(咽頭炎、副鼻腔炎)
- 下気道感染症(気管支炎、肺炎)
- 急性胃腸炎
- 尿管結石
- 尿路感染症(膀胱炎、腎盂腎炎)
- アレルギー性鼻炎
- 虫刺され
- 脱水症
- 熱中症
慢性疾患
- 糖尿病
- 高血圧
- 脂質異常症(高コレステロール血症)
- 痛風(高尿酸血症)
- 気管支喘息
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD、肺気腫)
- 頻尿(前立腺肥大、過活動膀胱)
- 骨粗鬆症
- 認知症
生活習慣病
当院では、生活習慣病の管理から急な体調不良まで、内科全般の診療を行っております。
生活習慣病は、飲酒や喫煙、ストレス、運動、食事といった日々の習慣が主な原因となる疾患群です。
遺伝的要因も発症に影響するため、ご家族に既往歴のある患者様は特に早期からの予防が重要となります。
多くは自覚症状に乏しいまま動脈硬化を進行させ、脳や心臓に重大な合併症を引き起こす危険があるため、健康診断で異常を指摘された際は必ずご受診ください。
糖尿病
 インスリンの分泌不足や作用低下により、血糖値が高い状態が続く疾患が糖尿病です。
インスリンの分泌不足や作用低下により、血糖値が高い状態が続く疾患が糖尿病です。
原因
一般的には遺伝、加齢、肥満、運動不足などが原因です。大半は、運動不足や食べ過ぎといった生活習慣の乱れが原因となる「2型糖尿病」で、全糖尿病の90〜95%を2型糖尿病が占めています。
多尿やのどの渇き、体重減少などの症状がありますが、自覚がないまま進行することも少なくありません。
放置すると、腎症や神経障害、網膜症といった合併症や、心筋梗塞や脳卒中など命に関わる病気を引き起こします。
治療
治療は運動療法と食事療法を基本とし、必要に応じて薬物療法も併用します。ガイドラインでは、合併症予防の観点からHbA1cの目標値は7%未満、対応する血糖値としては、空腹時血糖130mg/dl以下、食後2時間血糖値180mg/dl未満がおおよその目安とされています。
食事療法・運動療法を2-3ヶ月続けても血糖コントロール目標に達しない場合には、薬物療法の開始を考慮します。
高血圧
 血圧が基準値を超えて高い状態が続く疾患です。
血圧が基準値を超えて高い状態が続く疾患です。
かなりの患者さんの数が推定されていますが、約1/3はご自身の高血圧に気づいていないと考えられています。
高血圧の診断基準は、診察室での測定値が140/90mmHg以上、家庭血圧135/85mmHg以上とされていますが、正常血圧は120/80mmHg未満と厳格化されています。それ以上の正常高血圧でも早期からの治療介入が推奨されています。
高血圧の一部に白衣高血圧があります。白衣高血圧とは、診察室では高血圧を示し、診察室外では正常域血圧を示す状態です。診察室での血圧が14/90mmHg以上で、家庭血圧の平均が135/85mmHg未満の場合は、白衣高血圧の診断になります。
また、仮面高血圧という分類もあります。診察室では正常域血圧を示しますが、診察室外では高血圧を認める状態のことです。
原因
高血圧は喫煙や飲酒、ストレス、塩分の過剰摂取といった生活習慣が主な原因です。遺伝との関連も密接に考えられており、ご家族の中に高血圧のおられる方は要注意です。
家庭血圧による高血圧の診断は、朝・晩それぞれの測定値7日間の平均値を用います。
ほとんど自覚症状がないまま進行し、放置すると心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気を引き起こす危険があります。また慢性腎臓病や認知症進行の主要な因子とも考えられています。
治療では、運動療法や減塩を中心とした食事の見直しを行い、必要に応じて降圧剤による薬物療法も併用します。
減塩は食塩1日6g未満を目指します。食事内容は、野菜・果物・魚を積極的に摂取しコレステロールの少ない食事とします。運動は1日30分以上の有酸素運動を目安に行います。
治療
治療目標は、合併症のない75歳未満で130/80mmHg未満、合併症のない75歳以上で140/90mmHg未満と厳格化されています。脳血管障害(脳梗塞や脳出血が既往にある方)や心血管障害(心筋梗塞や狭心症が既往にある方)では130/80mmHg未満が目標です。
DASHダイエット、減塩、摂取エネルギー制限、飲酒の制限、エアロビックエクササイズなどによる生活習慣の改善が推奨されています。
脂質異常症
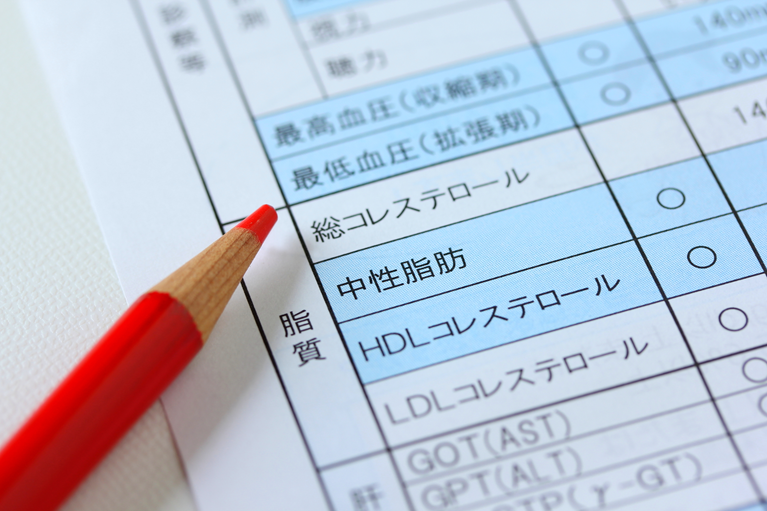 血液中の脂質の値が、基準から外れた状態を指します。
血液中の脂質の値が、基準から外れた状態を指します。
具体的には、中性脂肪が150mg/dl以上、LDL(悪玉)コレステロールが140mg/dl以上、HDL(善玉)コレステロールが40mg/dl未満のいずれかが該当します。
日本人では、男性の25%、女性の35%が該当すると考えられています。
LDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪が高いほど、心筋梗梗塞や脳卒中に発症リスクが増加し、HDL(善玉)コレステロールは低いほど、心筋梗梗塞や脳卒中に発症リスクが増加します。中性脂肪の著明な高値では急性膵炎の発症のリスクが上昇します。
原因
運動不足や肥満、過食、喫煙、飲酒といった生活習慣の乱れが主な原因となります。まれに、甲状腺機能異常や薬物が原因となる脂質異常症もあります。
自覚症状がないまま動脈硬化を進行させ、心筋梗梗塞や脳卒中といった命に関わる疾患のリスクを高めます。
治療の基本は、食事療法と運動療法です。
標準体重(身長(m)×身長(m)×22)を参考に目標体重を設定します。身体活動にあった1日摂取カロリーを計算し、脂肪エネルギー比20〜25%、炭水化物比50〜60%とします。食事内容としては、野菜、果物、未精製穀類、海藻類、大豆製品などの摂取を増やします。
特にLDL(悪玉)コレステロール高値を認める方には、それを低下させるために、飽和脂肪酸の摂取を減らし、不飽和脂肪酸の摂取を増やすことが大事です。またこれステロールの摂取を制限し、食物繊維の摂取を増やします。
特に中性脂肪の高値を認める場合は、それを低下させるために炭水化物、アルコールを制限し、ω3系多価不飽和脂肪酸の摂取を増やします。
治療
HDL(善玉)コレステロール低値を認める場合には、それを上昇させるために有酸素運動を継続するとともに、体重を減らし、トランス脂肪酸の摂取を避けます。
運動療法は、中等度の運動(持続可能な楽な、あるいはややきつい運動、速歩、スロージョギング、水泳、サイクリング)を1日30分以上、主3回以上できれば毎日行うことが推奨されます
3ヶ月後も目標値に達しない場合は、薬物療法も行います。治療開始後も定期的に血液検査を行い、薬効や副作用をチェックする必要があります。
痩せている患者様でも発症する可能性があるため、注意が必要です。
高尿酸血症(痛風)
 血液中の尿酸値が高くなる疾患です。尿酸値7mg/dlを高尿酸血症と定義されています。
血液中の尿酸値が高くなる疾患です。尿酸値7mg/dlを高尿酸血症と定義されています。
成人男性では20%程度がこの基準に当てはまります。
この尿酸が関節で結晶化すると、痛風発作と呼ばれる激痛が起こります。尿酸値が高いほど、痛風発作の危険が高まります。また尿路結石や腎障害のリスクにもなります。
痛風発作では、「関節が痛い、腫れた、歩けない、靴が履けない」などの訴えが多いです。
尿路結石では「お腹が痛い、赤い尿が出る」などの症状が多いです。
原因
プリン体を多く含むアルコールや赤身肉、レバーなどの過剰な摂取が主な原因です。
治療は、適切な強度の有酸素運動(運動療法)や適正エネルギー摂取、プリン体・果糖を控える食事療法、適切な飲水を基本とし、必要に応じて薬物療法も行います。薬物療法は長期にわたるため、定期的に血液検査を行い、薬効や副作用をチェックする必要があります。十分な水分摂取も大切です。
治療
痛風発作(急性痛風関節炎)を起こしているときは、NSAID、コルヒチンなどを使用して鎮痛を図ります。発作が完全に消退した後に尿酸降下薬を投与します。
メタボリックシンドローム
 内臓脂肪型肥満に加え、高血糖、高血圧、脂質異常のうち、2つ以上を合併している状態です。
内臓脂肪型肥満に加え、高血糖、高血圧、脂質異常のうち、2つ以上を合併している状態です。
原因
主な原因は、運動不足や食べ過ぎです。
自覚症状はほとんどありませんが、放置すると心筋梗塞や脳卒中など、命に関わる疾患のリスクが著しく高まります。
治療
治療では、食事療法と運動療法によって適正体重まで減量することが重要です。
当院で対応する検査
- 血液検査
- レントゲン検査
- 心電図検査
- 超音波検査
- 尿検査
発熱外来を開設しています
当院は、コロナ診療・検査医療機関です。
濃厚接触者の患者様や、37.5℃以上の発熱がある患者様の診療に対応しております。
当院では、患者様と医師、スタッフの安全を守るため、院内感染対策を徹底しています。
時間予約制と発熱患者様の診察室分離により、患者様同士の接触を最小限に抑えています。
また、手洗いやマスク装着、定期的な換気を徹底し、使用後の診察室は診察ごとに消毒しております。
発熱外来が対象となる症状
- 37.5℃以上の発熱
- 5日以内に始まった咳や喉の痛みなどの風邪症状がある患者様
- 息苦しさがある
- 味覚や嗅覚に異常を感じる
- 下痢や嘔吐が止まらない
検査について
当院では、抗原検査を実施しております。
検査を行うかは、患者様の希望や、症状や状況に応じて医師が判断いたします。
高熱など症状が強い場合は、ウイルス量が多いと想定されるため抗原検査で対応します。
鼻の奥に綿棒を挿入して検体を採取し、約15分で結果が判明します。
発熱外来の流れ
1予約
まずはWEB予約もしくは電話予約をしてください
WEB問診の入力をお願いします。
2ご来院
(お車でご来院の方)
駐車場に到着されましたら、電話にて到着連絡を行ってください。
車内で待機していただきます。
電話番号は、077-514-8205です。
(お車以外でご来院の方)
クリニックへ到着されましたら、発熱外来もしくは院内の受付前の椅子に座って待っていただきます。
院内が混雑する可能性もあるため、できるだけ車での来院をお願いします。
3診察・検査
問診票から新型コロナウイルス感染症、インフルエンザウイルス感染症が否定できない、または 検査を希望される方は、発熱外来で診察・抗原検査を実施いたします。(その際に気になる症状がありましたら併せてお伝えください)
3会計・処方
院内で会計・お薬の処方箋をお渡しいたします。