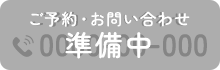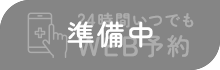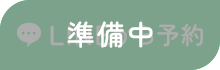癌化のリスクもある「胃炎」とは
 胃炎は、胃の内側を覆う粘膜に炎症が起きている状態です。
胃炎は、胃の内側を覆う粘膜に炎症が起きている状態です。
胃が荒れてしまい、胃痛や胸やけ、胃もたれ、吐き気などの症状が現れます。
しかし、人によってはほとんど症状がないまま進行していることもあります。
胃炎は、症状の有無に関わらず放置すると胃がんのリスクにつながることもあるため、注意が必要です。
胃の状態は胃カメラ(内視鏡検査)でしか正確に確認できません。
「ただの胃もたれ」「疲れかな」と自己判断せず、早めの検査をおすすめします。
胃炎の種類
胃炎は大きく急性胃炎・慢性胃炎・萎縮性胃炎の3つに分かれます。
それぞれ原因や病状が異なります。
急性胃炎
急性胃炎は、胃の粘膜が短期間で急に炎症を起こした状態です。
アルコールの飲みすぎや辛いものなどの刺激物、強いストレス、解熱鎮痛剤(NSAIDs)などが原因になることが多く、胃痛や吐き気、胸やけなどの症状が急に現れるのが特徴です。
原因を取り除き、胃酸を抑える薬などで治療すれば比較的短期間で治ることが多い病気です。
慢性胃炎
慢性胃炎は、胃の粘膜に慢性的な炎症が長期間続いている状態です。
多くはピロリ菌という細菌に感染していることが原因とされています。
症状は胃もたれや食欲不振、胃の不快感などが中心で、軽いために放置されやすいのが特徴です。
しかし慢性胃炎が進行すると、胃粘膜が徐々に傷んで萎縮性胃炎へ進むこともあるため、放置せず治療することが大切です。
萎縮性胃炎
萎縮性胃炎は、慢性胃炎が進行し、胃の粘膜が薄く弱くなって萎縮してしまった状態です。
胃酸や消化液を分泌する能力が低下していることが多く、自覚症状は少ないこともあります。
萎縮性胃炎は胃がんのリスクが高い前がん病変と考えられており、特にピロリ菌感染が長期間続いた方に多くみられます。
胃カメラで粘膜の萎縮の程度を確認し、必要に応じてピロリ菌除菌や定期的な検査を行うことが重要です。
うつる胃炎とうつらない胃炎
胃の不調や嘔吐が続くと、「これって感染する病気なの?」と不安に思われる方も多いと思います。
ここでは感染する病気(感染性胃腸炎)と胃炎の違いについてご説明します。
感染性胃腸炎とは?
感染性胃腸炎は、ウイルスや細菌が体に入ることで起こる感染症です。
ノロウイルスやロタウイルス、カンピロバクター、サルモネラ菌などが原因となり、嘔吐や下痢、腹痛、発熱を伴います。
感染した人の吐しゃ物や便などから人にうつる病気であり、家族や職場で集団感染することもあります。
胃だけでなく腸にも炎症が広がるため、「胃炎」ではなく「感染性胃腸炎」と呼ばれるのが一般的です。
胃炎は基本的に人にうつりません
胃炎(急性胃炎・慢性胃炎・萎縮性胃炎)は、胃の粘膜に炎症が起きている状態ですが、原因の多くは次の通りです。
- アルコールや刺激物
- ストレス
- 薬(痛み止めなど)
- ピロリ菌(※これは感染するため後で詳しく説明)
これらの胃炎は他人にうつる病気ではありません。
ピロリ菌と胃炎の関係
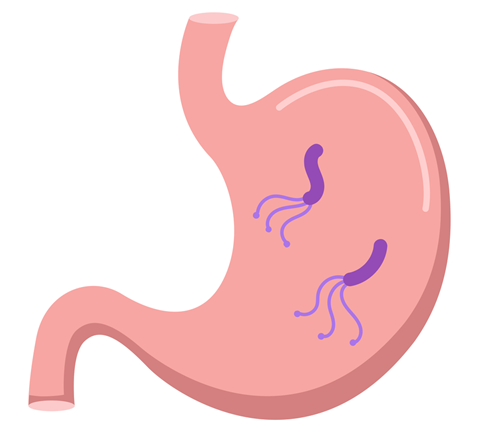 ピロリ菌は、胃の中にすみつく細菌で、日本人の多くが子どもの頃に感染するとされています。ピロリ菌が胃に感染すると、胃の粘膜が傷つきやすくなり、慢性的な炎症が起こります。これが慢性胃炎の大きな原因です。
ピロリ菌は、胃の中にすみつく細菌で、日本人の多くが子どもの頃に感染するとされています。ピロリ菌が胃に感染すると、胃の粘膜が傷つきやすくなり、慢性的な炎症が起こります。これが慢性胃炎の大きな原因です。
炎症が長く続くと、胃の粘膜が薄く弱くなり、萎縮性胃炎へと進行することもあります。萎縮性胃炎になると胃がんのリスクも高まるため、ピロリ菌の感染は非常に重要な病因と考えられています。ピロリ菌は検査で見つけることができ、薬で除菌することで胃炎の進行や胃がんの予防につながります。
胃炎の症状
胃炎では次のような症状が現れることがあります。

- 胃の痛み・みぞおちの痛み
- 胃もたれ・胃の重苦しさ
- 胸やけ
- 吐き気・嘔吐
- 食欲不振
- 胃の不快感
- お腹が張る感じ(膨満感)
- 空腹時の不快感
- 食後のムカムカ感
急性胃炎では突然症状が現れることが多く、慢性胃炎や萎縮性胃炎では軽い症状が長く続く傾向があります。
また、胃炎が進行していても症状が全く出ない場合もあるため注意が必要です。
胃炎の検査方法
胃炎の診断には、胃の粘膜の状態を直接観察できる胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)が最も重要です。
胃カメラでは、炎症の有無や程度、萎縮の進行状況、ピロリ菌感染の有無などを詳しく調べることができます。必要に応じて、胃の粘膜から小さな組織を採取し、病理検査を行うこともあります。
また、ピロリ菌の有無を調べるために、呼気検査や血液検査、便検査などの方法を併用することもあります。症状だけでは胃炎の種類や進行度を正確に判断できないため、胃の不調が続く場合は一度胃カメラ検査を受けることが大切です。当院では、苦痛の少ない経鼻内視鏡や鎮静剤を使った検査にも対応していますので、安心してご相談ください。
胃炎の治療法
胃炎の治療は、原因や胃の状態に合わせた方法で行います。基本的には次のような治療が中心です。
薬による治療
胃酸を抑える薬
胃の粘膜を守るために、胃酸の分泌を抑える薬を使います。これにより、炎症を鎮め、胃の痛みや不快感を和らげます。
胃の粘膜を保護する薬
傷ついた胃粘膜を守り、修復を助ける薬も併用することがあります。
ピロリ菌の除菌治療(慢性胃炎・萎縮性胃炎の場合)
ピロリ菌が原因の場合は、除菌治療が重要です。
抗生物質と胃酸を抑える薬を1週間程度服用することで、ピロリ菌を取り除きます。
除菌することで、胃炎の進行や胃がんのリスクを防ぐことができます。
食生活・生活習慣の改善
胃に負担をかけないようにすることも大切です。
- アルコールやコーヒー、刺激物を控える
- 暴飲暴食を避ける
- 食後すぐに横にならない
- ストレスをためない
日常生活の見直しも、胃炎の改善につながります。
胃炎を放置するとどうなる?癌化のリスク
胃炎は「ただの胃の不調」と思われがちですが、放置すると知らないうちに慢性胃炎や萎縮性胃炎に進行し、最終的には胃がんのリスクにつながることがあります。特に、ピロリ菌による慢性的な胃炎は前がん病変とも言われており、早期に発見し適切に対処することが大切です。
当院では、症状のある方はもちろん、症状のない方でも受けていただける内視鏡ドックを行っています。
「最近胃の調子が気になる」「健康診断では異常なしだったけれど心配」という方は、ぜひ一度当院の内視鏡ドックで胃の状態を詳しくチェックしてみませんか?
胃がん予防のためにも、症状がなくても一度検査を受けてみることをおすすめします。
よくある質問
胃炎はストレスでも起こりますか?
はい。ストレスは胃酸の分泌を増やしたり、自律神経を乱すことで胃の粘膜を傷つけ、ストレス性胃炎の原因になります。
胃炎で発熱することはありますか?
通常、胃炎だけで高熱が出ることはほとんどありません。ただし、感染性胃腸炎の場合は、発熱や全身症状を伴うことがあります。
胃炎は何日で治りますか?
急性胃炎なら通常数日〜1週間程度で治ることが多いです。慢性胃炎や萎縮性胃炎の場合は長期的な治療や経過観察が必要です。
胃炎のときに食事で気をつけることはありますか?
胃炎の時は脂っこいもの、辛いもの、アルコールは控えましょう。消化の良いおかゆやスープなどを中心に、胃に優しい食事を心がけてください。
胃炎でゲップが増えることはありますか?
はい。胃炎によって胃の働きが低下し、胃の中に空気がたまりやすくなることで、ゲップが増えることがあります。
胃炎は睡眠不足でも悪化しますか?
睡眠不足はストレスや自律神経の乱れにつながるため、胃炎の悪化要因になります。規則正しい生活を心がけましょう。
胃炎のときにコーヒーは飲まない方がいいですか?
はい。コーヒーは胃酸を刺激するため、胃炎の症状がある間は控えることをおすすめします。
胃炎があると空腹時に痛くなるのはなぜですか?
胃炎があると胃酸が胃粘膜を刺激し、空腹時に痛みや不快感を感じることがあります。早めの受診をおすすめします。
胃炎はアルコールが原因になることもありますか?
はい。アルコールは胃粘膜を直接刺激し、急性胃炎の原因になります。飲酒後に胃痛や胸やけがある方は注意が必要です。
胃炎は風邪からも起こりますか?
風邪そのものが胃炎の原因になることはありませんが、風邪薬や解熱鎮痛剤の影響で薬剤性胃炎を起こすことがあります。
胃炎が治るまで食事はずっとおかゆだけですか?
症状が落ち着いてきたら、少しずつ普通の食事に戻して大丈夫です。急に脂っこいものは避け、胃の様子を見ながら食事を調整しましょう。
胃炎は一度治ればもう再発しませんか?
生活習慣が乱れていたりピロリ菌が残っていると、胃炎は再発することがあります。胃の状態によっては定期的な経過観察が必要です。
胃炎のときに冷たいものは控えた方がいいですか?
冷たい飲み物は胃腸の働きを弱めることがあるため、胃炎がある間は常温〜温かい飲み物の方が望ましいです。
胃炎で胸が痛いことはありますか?
胃酸が逆流することで胸のあたりに違和感や痛みを感じることがあります。逆流性食道炎を併発している可能性もあります。
胃炎で便が黒くなることはありますか?
胃炎が悪化して胃粘膜から出血した場合、便が黒くタール状になることがあります。黒い便が出た場合は、早めに医療機関を受診してください。