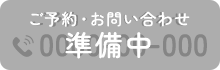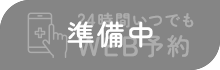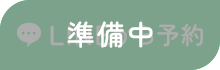腸炎とは
 腸炎とは、腸に炎症が起こる病気の総称です。
腸炎とは、腸に炎症が起こる病気の総称です。
原因はさまざまで、ウイルスや細菌の感染によって起こるケースが多いですが、食事の乱れやストレス、自己免疫異常が関係していることもあります。
ウイルス性腸炎や細菌性腸炎などの急性腸炎は短期間で治ることが多い一方で、潰瘍性大腸炎やクローン病など慢性腸炎として長期間続く場合もあります。
「単なる下痢」と思わず、早めに適切な診断と治療を受けることが大切です。
腸炎の種類と原因
腸炎は、原因によって以下の4つに分けられます。
ウイルス性腸炎(感染性腸炎)
ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスが原因の腸炎で、冬に多く発生します。嘔吐・下痢・発熱などが突然起こり、感染力が強いため人にうつることが特徴です。
細菌性腸炎
サルモネラ菌やO-157などの細菌が原因となる腸炎です。食中毒として発症することが多く、高熱や激しい腹痛、血便を伴うこともあります。感染力が強いです。
急性腸炎
ウイルスや細菌感染が原因となり、短期間で発症・改善する腸炎です。数日〜1週間ほどで自然に回復することが多いですが、脱水症状には注意が必要です。
慢性腸炎(非感染性)
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患がこれにあたります。長期間腸に炎症が続きますが、感染症ではないため人にうつることはありません。専門的な治療と定期管理が必要です。
腸炎の主な症状
腸炎では以下のような症状がみられます。

- 下痢(水様便や軟便)
- 腹痛(差し込むような痛み)
- 吐き気・嘔吐
- 発熱・全身のだるさ(倦怠感)
- 血便(特に細菌性腸炎で見られることがある)
これらの症状が続く場合は、「軽い胃腸炎」と自己判断せず、早めの受診をおすすめします。
腸炎はうつる?感染に注意が必要な腸炎
腸炎の中には人にうつるタイプと、うつらないタイプがあります。特に注意が必要なのは、ウイルスや細菌が原因となる「感染性腸炎」です。
うつる腸炎(感染性腸炎)
- ウイルス性腸炎(ノロウイルス・ロタウイルスなど)
- 細菌性腸炎(サルモネラ菌・カンピロバクター・O-157など)
これらは接触感染や飛沫感染で周囲の人にうつるため、感染予防がとても重要です。嘔吐物や下痢便に含まれるウイルス・細菌が手指や物を介して広がります。
うつらない腸炎
- 潰瘍性大腸炎
- クローン病(炎症性腸疾患)
これらは感染症ではないため、人にうつる心配はありません。周囲の方は普段通りの接し方で問題ありません。
感染予防のポイント
- トイレ後や調理前後の手洗いを徹底する
- 嘔吐物や便の処理は使い捨て手袋・マスク着用で行う
- タオル・食器の共用は避ける
- 嘔吐物・便は次亜塩素酸系の消毒剤でしっかり消毒
「腸炎=必ず感染する」とは限りませんが、下痢や嘔吐の症状がある場合は周囲への配慮を忘れず、早めの受診・治療を心がけましょう。
腸炎の検査方法
腸炎は症状だけでは原因が分からないため、必要に応じて次のような検査を行います。
血液検査
腸の炎症が起きているかどうかを確認するために、白血球数やCRP(炎症反応)を調べます。細菌感染が疑われる場合は、炎症の数値が高くなっていることが多いです。
便検査
便を採取して、ウイルスや細菌の有無を調べます。
ノロウイルスやロタウイルス、サルモネラ菌、O-157など、感染の原因が特定できる場合もあります。
大腸カメラ
(下部消化管内視鏡検査)
症状が長引いている場合や、慢性腸炎(潰瘍性大腸炎・クローン病など)の疑いがある場合は、大腸カメラで腸の粘膜を直接観察します。
腸の内部の潰瘍や炎症の状態を詳しく確認できます。
超音波検査(腹部エコー)
腸の状態(腸管の腫れ・むくみなど)を調べるために腹部エコー検査を行うこともあります。
腸の動きや、周囲に異常がないかを簡便に確認できます。
腸炎の治療方法
腸炎の治療は原因や症状の重さによって異なりますが、基本的には以下のような方法で治療を行います。
脱水予防(点滴・経口補水液)
下痢や嘔吐で水分や電解質が失われるため、脱水症状にならないよう水分補給が最優先です。
軽症の場合は経口補水液(OS-1など)での水分補給を、自力で水分が取れない場合は点滴治療を行います。
整腸剤・止痢薬
症状に応じて整腸剤(ビフィズス菌など)や、必要に応じて止痢薬(ロペラミドなど)を使用します。ただし、細菌性腸炎などで原因となっている細菌を排出する必要がある場合は、止痢薬を使わないこともあります。
抗生物質
細菌性腸炎の場合には、症状や重症度に応じて抗生物質を使用します。
ウイルス性腸炎には抗生物質は効果がありませんので、安易な使用は避けます。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)の治療
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)などの慢性腸炎の場合は、消炎薬(5-ASA製剤)や免疫調整薬、生物学的製剤などを用いた専門的な治療が必要です。定期的な検査と経過観察も大切です。
腸炎は適切な治療を行えば改善する病気ですが、脱水や重症化を防ぐためにも自己判断せず早めに受診することが大切です。
腸炎は何日で治る?受診の目安
軽いウイルス性腸炎や食あたりによる腸炎の場合は、2~5日ほどで自然に改善することが多いです。
その間は水分補給と安静を心がけましょう。
ただし、次のような場合は医療機関の受診をおすすめします。

- 高熱(38℃以上)が続く
- 激しい腹痛や我慢できない腹部の張りがある
- 血便が出る
- 下痢や嘔吐が長引く(3日以上続く)
- 水分が摂れない、脱水が心配な場合
- 小さなお子様や高齢の方、持病がある方
また腸炎には合併症も知られており、カンピロバクター腸炎にはギラン・バレー症候群や過敏性腸症候群などが続発することが稀にあると報告されています。
これらの症状がある場合は、細菌性腸炎や重症の腸炎の可能性があるため、早めの受診・検査が安心です。
腸炎は適切に対処すれば回復できる病気ですが、自己判断せずに相談することが大切です。
腸炎の過ごし方と食事
腸炎と診断された場合は、次のポイントに注意して自宅で安静に過ごしましょう。症状が軽くても、体力の消耗や脱水に注意が必要です。
脱水対策(水分・経口補水液)
 下痢や嘔吐で水分と塩分が失われるため、こまめな水分補給が大切です。
下痢や嘔吐で水分と塩分が失われるため、こまめな水分補給が大切です。
経口補水液(OS-1など)がおすすめですが、スポーツドリンクや薄めたみそ汁なども有効です。
一度に大量に飲むと吐いてしまう場合があるため、少量ずつ、こまめに飲むことを心がけましょう。
刺激の少ない食事
 症状が落ち着いてきたら、胃腸に優しい食事から少しずつ再開します。
症状が落ち着いてきたら、胃腸に優しい食事から少しずつ再開します。
おすすめはおかゆ・うどん・具の少ないスープなど消化の良いもの。脂っこいものや乳製品、カフェイン、香辛料は避けましょう。無理に食べず、食べられる範囲でゆっくり回復させましょう。
胃腸への負担を減らす(食事制限・安静)
腸が炎症を起こしている間は、できるだけ安静に過ごし、食事も無理をしないことが大切です。
症状が強い時は食事を控え、水分補給だけにするのも有効です。無理に食べると症状が悪化することがあります。
腸炎は安静と水分補給で回復することが多いですが、症状が重い・長引く場合は早めに医療機関へご相談ください。
よくある質問
ビブリオ菌による腸炎とは?
夏場に魚介類の生食で感染しやすいのがビブリオ菌です。腹痛や下痢を起こす細菌性腸炎の一種です。
腸炎で処方される薬にはどんなものがありますか?
整腸剤、止痢薬、吐き気止めがよく使われます。細菌性腸炎の場合は抗生物質を処方することもあります。
腸炎で熱が出たときはどうすればいいですか?
軽い発熱は体の防御反応なので、安静と水分補給が大切です。高熱(38.5℃以上)や発熱が続く場合は受診しましょう。
腸炎のときに解熱剤は飲んでいいですか?
強い発熱でつらい場合はアセトアミノフェンなどの解熱剤を使用してもかまいません。ただし下痢や嘔吐が続く場合は受診して相談をしてください。
腸炎はストレスが原因で起こることはありますか?
細菌やウイルス以外に、過敏性腸症候群などのストレス性腸炎もあります。原因によって治療法が異なります。
腸炎の時に飲む薬は市販薬で代用できますか?
整腸剤や下痢止めなどの市販薬で対処できる場合もありますが、症状が重い場合や長引く場合は早めの受診をおすすめします。
腸炎で血便が出た場合は何の病気ですか?
細菌性腸炎(O-157やサルモネラなど)で血便が出ることがあります。重症化することもあるため、すぐに医療機関を受診しましょう。
腸炎は夏と冬どちらが多いですか?
ウイルス性腸炎は冬に流行し、細菌性腸炎(ビブリオ菌やカンピロバクター)は夏に増える傾向があります。
腸炎のときに抗生物質は必ず必要ですか?
ウイルス性腸炎には抗生物質は不要です。細菌性腸炎と診断された場合のみ抗生物質を使用します。
腸炎の熱は何日くらい続きますか?
ウイルス性腸炎なら1~2日程度の軽い発熱で治まることが多いです。高熱や長引く場合は別の原因が疑われます。
腸炎になったときスポーツドリンクだけで大丈夫ですか?
軽症なら問題ありませんが、経口補水液(OS-1など)のほうが脱水予防には適しています。
腸炎で吐き気が強いときはどんな薬を使いますか?
必要に応じて吐き気止め(制吐剤)が処方されます。自分で市販の吐き気止めを使用する前に、医師に相談することをおすすめします。
腸炎で腹痛がひどいときは鎮痛薬を飲んでもいいですか?
腹痛が強い場合でも自己判断で痛み止めは控えた方が安心です。特に解熱鎮痛剤は腸に負担をかけることがあります。
腸炎は大人でもうつりますか?
ウイルス性・細菌性腸炎は大人でも感染します。手洗い・消毒など家庭内感染の予防が重要です。手指衛生とともに適切な消毒(細菌性では逆性石鹸やアルコール、ウイルスでは次亜塩素酸ナトリウムや加熱)を行いましょう。
腸炎で何度も再発するのはなぜですか?
急性腸炎が繰り返される場合は、過敏性腸症候群や炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)など慢性的な腸の病気が隠れていることもあります。消化器内科で相談をしてください。