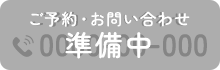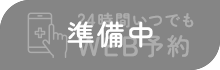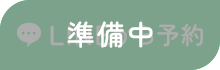- 疲れやすい、疲れが取れないという方へ
- 疲れやすい・疲れが取れない原因は?
- 疲れが取れないときに疑う病気
- 疲れやすい、疲れが取れないときの対処法
- 疲れやすい、疲れが取れない場合の検査
- 疲労感が継続する場合は当院までご相談ください
疲れやすい、疲れが取れないという方へ
 疲労や体力の低下を「年齢のせい」と諦めてしまう患者様は少なくありません。
疲労や体力の低下を「年齢のせい」と諦めてしまう患者様は少なくありません。
疲れの原因は、「精神的なもの」「神経的なもの」「肉体的なもの」に大別され、相互に影響し合います。
こうした疲労を放置すると慢性化して日常生活に支障をきたし、新たな病気を誘発することもあります。
長引く強い倦怠感は病気のサインかもしれないため、当院の受診をおすすめします。
疲れやすい・疲れが取れない原因は?
体がすぐに疲れてしまうときのおもな原因は以下のことが考えられます。
睡眠不足
睡眠不足は、患者様の疲労が蓄積する大きな要因です。
身体の回復が追いつかないだけでなく、記憶を整理するといった脳の重要な機能にも支障をきたします。
特に注意すべきは、睡眠の「質」です。
たとえ十分な睡眠時間を確保しても、その質が低ければ、患者様の疲労は十分に回復しないためです。
栄養不足
患者様が疲れやすさを感じる背景には、特定の栄養素の不足が隠れていることがあります。
ビタミンB群は、糖質やたんぱく質、脂質からエネルギーを産生する際に不可欠な栄養素です。
特にビタミンB1・B2・B6が不足すると、エネルギー産生が滞り、疲労感に繋がります。
鉄分は、全身の細胞へ酸素を供給する重要な役割を担っています。
不足すると、息切れや食欲不振、倦怠感といった貧血症状を引き起こします。
特に月経のある女性の患者様は、不足しやすいため注意が必要です。
たんぱく質は、骨や血液、臓器など、患者様のお身体を構成する基本となる栄養素です。
不足すると筋肉量が減少し、貧血や疲労感の原因となります。
糖質は、活動の主要なエネルギー源であり、体内でブドウ糖に分解され、細胞に供給されます。
不足するとエネルギー切れを起こし、疲れやすさを感じるようになります。
運動不足
運動不足は代謝や血流を悪化させ、疲労物質が体内に蓄積しやすくなる原因です。
特に、長時間のデスクワークなどで同じ姿勢を続ける患者様は、筋肉の緊張から血行不良を招きがちです。
その結果、慢性的な疲労感に繋がることがあります。
精神的なストレス
人間関係や仕事上の悩み、環境の変化といったストレスは、自律神経の乱れを招き、患者様は身体のだるさを感じます。
通常、ストレスの原因がなくなれば、このだるさも自然と解消されます。
しかし、ストレスを放置すると、うつ病などの精神疾患に繋がる危険性があるため注意が必要です。
女性ホルモンの乱れ
女性の患者様の場合、月経周期に伴うだるさを感じることがあります。
これは、女性ホルモンのバランスが変動することで生じるPMS(月経前症候群)の一症状です。
PMSでは、乳房の張りや肌荒れ、イライラといった症状とともに、だるさが代表的なサインとして現れます。
特に月経前1週間の不調は、PMSによる可能性が考えられます。
感染症
患者様が風邪をひかれた際、その発症初期や回復期にだるさを感じることがあります。
だるさの強さは、原因となるウイルスの種類によって様々です。
また、体のだるさは風邪に限らず、急性肝炎やインフルエンザといった他の疾患が原因の場合もございます。
疲れが取れないときに疑う病気
疲れがなかなか取れない時は、以下のような病気の可能性があります。
糖尿病
糖尿病の患者様は、インスリンの作用不足や分泌低下により、慢性的な高血糖状態に陥ります。
高血糖が続くと、体重減少やのどの渇き、疲れやすさといった症状が現れます。
一方、低血糖の状態では、身体の主要なエネルギー源であるブドウ糖が不足します。
その結果、冷や汗やふらつき、そして疲労感といった症状が見られます。
睡眠時無呼吸症候群
この疾患の患者様は、睡眠中に呼吸が止まったり弱まったりする状態を繰り返します。
その結果、睡眠の質が著しく低下し、起床時に疲れが残る、すっきり目覚められないといった症状を自覚します。
日中にも強い眠気に襲われることも少なくありません。
慢性疲労症候群
この疾患は、患者様の日常生活に支障をきたすほどの激しい疲労感が、半年以上続く状態を指します。
強いストレスを契機に発症することが多く、それまで健康に過ごされていた患者様が突然発症することもあります。
重度の疲労感に加えて、関節痛や腹痛、筋肉痛、抑うつ症状、頭痛、不眠、集中力の低下、脱力感など、多彩な症状が現れる可能性があります。
貧血
血液中のヘモグロビンは、全身に酸素を運搬する重要な役割を担っています。
貧血になるとこのヘモグロビンが減少し、体内が酸素不足に陥ります。
その結果、患者様はふらつきやめまい、立ちくらみ、疲れやすさといった症状を経験します。
原因として、悪性腫瘍や血液疾患、胃潰瘍などからの出血が考えられ、女性の患者様では月経も一因となります。
疲れやすい、疲れが取れないときの対処法

疲れやすい、疲れが取れない時の対処法を紹介します。
十分な睡眠を確保する
質の高い睡眠は、患者様の身体のだるさを回復させる上で効果的です。
起床・就寝の時間を一定に保つことや、朝に太陽光を浴びて体内時計を整えるといった習慣を、当院ではおすすめしております。
生活習慣の見直し
不規則な生活は体内時計を乱し、睡眠不足などを招いて患者様にだるさを感じさせます。
特に就寝時間が不規則な方は体内時計が乱れやすいため、日々の生活リズムを一定に保つことが重要です。
適度な運動
患者様が身体のだるさを理由に動かないでいると、かえって症状が悪化します。
筋力の低下や血行不良を招き、疲労感をさらに増幅させてしまうためです。
当院ではだるさの解消法として、体操やウォーキングといった適度な有酸素運動を患者様におすすめしております。
バランスの取れた食事
偏った食生活を送る患者様は、エネルギーが不足し、だるさを感じやすくなります。
中でもビタミンB群の欠乏には、特に注意が必要です。
ストレス解消
ストレスへの対処法を習得すると、患者様の精神は安定します。
また、自律神経の乱れがもたらす倦怠感の予防にも繋がります。
音楽鑑賞や深呼吸、趣味など、ご自身が最も安らげる方法を見つけることを、当院は推奨しています。
疲れやすい、疲れが取れない場合の検査
 長引く倦怠感の背景には、何らかの疾患が潜んでいる可能性がございます。
長引く倦怠感の背景には、何らかの疾患が潜んでいる可能性がございます。
当院では患者様への丁寧な問診を通じて、原因究明に必要な検査を実施いたします。
血液検査で、糖尿病や貧血の有無、甲状腺ホルモンや抗体の数値を分析し、甲状腺疾患の可能性を精査します。
また、肝機能障害が倦怠感の原因となっていないか、肝臓の状態を詳しく評価します。
感染症を評価し、倦怠感の原因として考えられる感染症の有無を特定します。
カリウムやナトリウム、クレアチニンといった電解質の均衡状態を調べます。
心電図では、心臓の機能に異常がないかを調べ、倦怠感との関連性を評価します。
超音波検査では、甲状腺疾患の可能性を視野に入れ、甲状腺の大きさや腫れ、結節の有無といった形態的な異常がないか精査します。
疲労感が継続する場合は当院までご相談ください
 現代社会において、疲労は誰にとっても身近な問題です。
現代社会において、疲労は誰にとっても身近な問題です。
その原因は一つとは限らず、複数の要因が重なって生じることも少なくありません。
ご自身の状態に合わせた方法で、疲労回復を図ることが重要です。
しかし、セルフケアをしても改善しない倦怠感は、何らかの疾患が兆候として現れている可能性があります。
病気が原因であれば専門的な治療を要するため、長引く疲労にお悩みの患者様は、我慢なさらずお早めに当院へご相談ください。