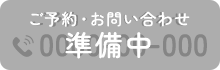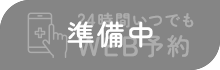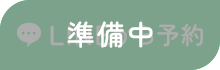- 胃からくる口臭はどんなにおい?
- 口臭の主な3つの原因
- 胃からくる口臭がある場合に疑う病気
- 胃からくる口臭の場合の検査
- 胃が原因の口臭の対策方法
- 口が原因の口臭の対策方法
- 胃からくる口臭かも…と心配な方は当院までご相談ください
胃からくる口臭はどんなにおい?
 胃の機能が低下すると、食べた物が十分に消化されず、胃の中で異常発酵を起こします。この際に発生した臭気が肺を経由して呼気となるため、患者様の口臭は強くなります。
胃の機能が低下すると、食べた物が十分に消化されず、胃の中で異常発酵を起こします。この際に発生した臭気が肺を経由して呼気となるため、患者様の口臭は強くなります。
また、逆流性食道炎の患者様では、こみ上げてきた胃液によって酸っぱい口臭が生じます。胃の不調が原因の場合、口臭では、何かが発酵したかのような臭い、ツンとくる臭い、酸っぱい臭いなどの特徴があります。
口臭の主な3つの原因
口臭が強くなる原因には、さまざまなものがあります。ここでは、大きく3種類に分けてご紹介します。
お口のトラブル、食事の影響
口臭は、舌苔やドライマウス、歯周病、虫歯といった口腔内の問題によっても引き起こされます。疾患に至らない場合でも、お口の中が不衛生であれば臭いは強まります。毎日の丁寧なブラッシングや、歯科での定期的なクリーニング、専門的な治療によって改善が見込めます。
歯茎の腫れや歯の痛みがある患者様は、まずは歯科を受診されることを当院は推奨しています。なお、ニンニクなど食品由来の口臭は一過性で、時間の経過とともに治まります。
消化管のトラブル
ピロリ菌感染や胃がん、胃・十二指腸潰瘍、胃炎、逆流性食道炎といった消化器疾患が、患者様の口臭の原因となる場合があります。また、便秘によって体内に滞留した排泄物が腐敗し、その物質が血液を介して肺に運ばれることで、強い口臭が発生することもあります。
当院では胃カメラ検査などで原因を特定し、適切な治療を行うことで口臭の改善が期待できます。過度なダイエットによってエネルギー不足になると、体内でケトン体という物質が発生します。このケトン体が、口臭の原因になることがあります。
その他
過度なダイエットによるエネルギー不足は、口臭の原因となるケトン体を体内で発生させます。また、扁桃炎や副鼻腔炎(蓄膿症)、肝機能の低下、糖尿病といった疾患が原因で、口臭が強くなることもあります。
胃からくる口臭がある場合に疑う病気
主に、以下のような疾患が挙げられます。
慢性胃炎
消炎鎮痛薬の副作用やストレス、ピロリ菌感染は、慢性胃炎の原因となります。
患者様には、腹部不快感や吐き気、食欲不振、腹痛といった症状とともに、口臭の悪化がみられることがあります。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
胃・十二指腸潰瘍は、ストレスやピロリ菌感染、食生活の乱れ、消炎鎮痛剤の副作用などが引き起こす疾患です。
胃や十二指腸の粘膜に、びらんや潰瘍が生じます。患者様には、食欲不振やげっぷ、吐き気、体重減少、胸やけ、みぞおちの痛みといった症状に加え、口臭が悪化することがあります。
胃がん
初期の胃がんは自覚症状に乏しい疾患です。
進行すると、患者様には腹痛や胸やけ、食欲不振、吐血や下血などの症状に加え、口臭も現れます。国内では高齢化に伴い、罹患者数が増加しています。
その他
糖尿病や扁桃炎、副鼻腔炎といった疾患が、患者様の口臭を悪化させる原因となる場合があります。
胃からくる口臭の場合の検査
 当院では、口臭治療の第一歩として、患者様の的確な診断を重視しています。
当院では、口臭治療の第一歩として、患者様の的確な診断を重視しています。
胃カメラ検査による消化管の直接観察や、ピロリ菌の感染検査を実施します。これらの精密な検査結果は、無駄のない効果的な治療計画を立てるために不可欠です。
また、カウンセリングにも時間をかけ、患者様の食習慣や生活習慣を踏まえた治療方針をご提案します。口臭に悩まない快適な生活を、当院が長期的にサポートいたします。
胃が原因の口臭の対策方法
胃に原因がある口臭は、消化器内科での診療と、生活習慣の見直しが効果的です。
医療機関で消化器疾患の有無を確認する
胃潰瘍や慢性胃炎、ピロリ菌感染などの胃の病気が口臭の原因となることがあります。これらは自覚症状が少ないこともあるため、口臭が続く場合は、消化器内科での検査をおすすめします。特に、空腹時に強く感じる口臭や、げっぷに伴う臭いがある場合は、胃の状態に問題がある可能性があります。
当院では、必要に応じて内視鏡検査やピロリ菌検査を実施し、適切な治療をご案内いたします。
ピロリ菌感染の治療を行う
ピロリ菌に感染している場合、胃の炎症や胃酸の逆流が慢性的に起こり、口臭の原因となります。
ピロリ菌は除菌治療によって改善が見込めるため、検査結果に応じて専門医の指導のもと、適切な薬剤による治療を受けましょう。除菌後も胃の粘膜に炎症が残ることがあるため、定期的なフォローアップも重要です。
食生活を整える
脂っこい食事やニンニク、アルコール、コーヒーなどは胃に負担をかけ、胃の不調からくる口臭を悪化させる原因になります。消化の良い食品を選び、よく噛んでゆっくり食べることが胃の負担を減らすポイントです。
また、過度な空腹状態も胃酸の分泌を促し、口臭につながるため、適度な間食や規則正しい食事を心がけましょう。
ストレス管理と睡眠の質を見直す
ストレスは自律神経の乱れを引き起こし、胃酸過多や逆流性食道炎の悪化につながることがあります。その結果、胃の不調からくる口臭を引き起こすこともあります。適度な運動や十分な睡眠、リラックスできる時間を確保することで、胃の働きが整いやすくなります。
当院では、ストレスが胃腸に及ぼす影響も踏まえた生活指導を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
口が原因の口臭の対策方法
口の中に原因がある場合の口臭対策は、歯科医院での治療と正しい口腔ケアです。
歯医者さんで治療を受ける
虫歯や歯周病は自然に治癒することはなく、放置すると口臭が悪化するため、歯科医院での治療が最も有効です。患者様がご自宅でのケアを徹底されていても、歯石は少しずつ付着します。そのため、数ヶ月に一度は歯科医院で歯周病のチェックや歯石の除去を受けることを推奨しています。被せ物などの劣化も口臭の原因となるため、併せて確認してもらうと良いでしょう。
また、ドライマウスの対策として、食事の際によく噛み、舌や顎の筋肉を動かして唾液の分泌を促すことが大切です。それでも改善が見られない患者様は、一度歯科医院に相談し、適切な治療を受けることをお勧めします。
正しい歯磨きを習得する
就寝前と起床時の1日2回の歯磨きを習慣にしましょう。歯磨き粉は小豆2粒程度を目安とし、泡立ちで満足せず隅々まで磨くことが肝心です。
歯ブラシだけでは清掃が不十分なため、デンタルフロスを併用し、細菌の繁殖しにくい口腔環境を保つことを推奨します。お子様の患者様の口臭は、磨き残しが主な原因です。保護者の方による仕上げ磨きを必ず行ってください。
舌磨きをする
舌苔は、舌表面の清掃によって除去できます。
患者様の舌はデリケートですので、力の入れ過ぎは禁物です。ガーゼや舌専用のブラシを用い、歯磨きの3分の1程度の力で、奥から手前へ優しく掻き出してください。このケアは数日に一度の頻度で実施することを、当院は推奨しています。
唾液の分泌を促す
食事の際、意識してよく噛むことで唾液の分泌は促されます。唾液腺のマッサージを併せて行うことも、当院は推奨しています。
また、患者様が服用されている花粉症の薬には、副作用として唾液量を減少させるものがございます。唾液分泌への影響が少ない薬もございますので、鼻炎薬を服用中の患者様は、薬剤師や医師までご相談ください。
胃からくる口臭かも…と心配な方は当院までご相談ください
 口臭が気になる際、多くの患者様はまずお口の中を原因と考えられます。
口臭が気になる際、多くの患者様はまずお口の中を原因と考えられます。
実際に歯周病や虫歯が原因の場合も多く、歯茎の腫れや歯の痛みがあれば、歯科受診を当院は推奨します。しかし、セルフケアで改善しない、あるいは便秘や呑酸(酸っぱいものがこみ上げる感覚)、その他胃腸の不調を伴う口臭は、消化器疾患が原因かもしれません。
その際は、当院の消化器内科へご相談ください。胃カメラ検査などで正確に診断し、患者様に合った適切な治療をご提供します。